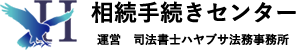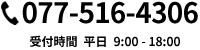相続に関する基礎知識
相続財産の範囲について
不動産や預貯金、株式などの有価証券などの財産のほかに、ローンや借入、未払いの税金などの負債も含まれます。
相続人とは
配偶者は常に相続人となり、以下子供→親→兄弟の順に相続権が発生します。
法定相続分とは
◇配偶者と子が相続人の場合
配偶者 2分の1
子供 2分の1
◇配偶者と親が相続人の場合
配偶者 3分の2
親 3分の1
◇配偶者と兄弟が相続人の場合
配偶者 4分の1
親 4分の1
代襲相続とは
被相続人が死亡する以前に相続人である子供又は兄弟が死亡していた場合、その子供が代襲して相続権を得ます。
遺留分とは
相続人に最低限保証された相続分のことです。
具体的には法定相続人分の2分の1が遺留分として保証されます。
ただし兄弟姉妹には遺留分は保証されません。
また、遺留分は請求しない限りもらえません。
相続人がいない場合の相続財産について
原則、国庫に帰属しますが、例外として被相続人と生計を同一にしていた者、または被相続人の療養看護に努めた者等被相続人と特別の縁故があった者に帰属することがあります。
遺言書がある場合
公正証書遺言の場合には家庭裁判所の検認手続きは不要ですが、自筆証書遺言が見つかった場合は原則として家庭裁判所の検認手続きが必要です。
ただし、自筆証書遺言であっても遺言書保管制度を利用して法務局で保管されていた遺言書に関しては検認手続きが不要となります。
検認とは
遺言書の発見者や保管者が家庭裁判所に遺言書を提出して相続人立合いのもとで、遺言書の開封し、遺言の内容を確認することです。
ただし、検認は遺言内容についての形式が整っているかどうかを判断するもので遺言の効力を証明するものではありません。
遺言書の種類について
自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
遺言書がない場合
法定相続分に応じて相続するか、相続人全員で遺産分割協議を行い財産の分け方を決定することになります。
遺産分割の方法
一般的な分割方法として現物分割、代償分割、換価分割の3つの方法があります。
①現物分割
相続財産をそのままの形で分ける方法です。
例えば、不動産は相続人A、預貯金は相続人B、株式は相続人Cが取得するといった分け方です。
②代償分割
相続財産をもらった人が、その代償として他の相続人に金銭を支払うといった方法です。
例えば、不動産を相続した相続人Aが、相続財産をもらう代わりに相続人Bに1000万を支払うといった方法です。
③換価分割
相続財産を現金に換えて現金を分割する方法です。
例えば、相続財産が不動産しかなかった場合に不動産を売却して売却代金を相続人で分けるといった方法です。
遺産分割が整わなかった場合
家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになります。
遺産分割調停とは、裁判官と調停委員で組織される調停委員会が、中立公正な立場で、当事者双方の言い分を平等に聞いて具体的な解決策を提案するなどして円満解決できるよう斡旋する手続きです。
相続したくない場合
自分が相続人であることを知った日から3か月以内に被相続人が死亡した住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。
相続税の基礎控除額
3,000万円+600万円×法定相続人の人数が基礎控除額になります。